「また野菜だけ残してる…」「どうしたら食べてくれるの?」
こんなふうに、3歳児の野菜嫌いに悩むママは少なくありません。
実は、3歳児の野菜嫌いにはきちんと理由があります。
この記事では、保育園で子どもと向き合ってきた調理師の視点で、野菜嫌いの理由と克服法をわかりやすく紹介します。
毎日のごはん時間がもっと楽しくなる、5つのヒントを参考にしてみてください。
「手作りしたいけど、毎日野菜を揃えるのは大変…」
そんなママには、旬の野菜がセットで届くオイシックスもおすすめです。簡単に栄養たっぷりの野菜を準備できるので、忙しい日でもすぐにごはん作りに取りかかれます。
3歳児が野菜を食べない理由は?

「数えるほどしか食べさせてないのに…」「離乳食の時は好き嫌いなく食べていたのに、いつの間にか野菜嫌いに…」
子ども1歳を過ぎると自我が出てき、好き嫌いが増えることが多くなります。特に2~3歳のタイミングで野菜嫌いが始まります。
子どもは苦味や酸味に敏感
3歳の子どもは、大人よりも酸味や苦味に敏感です。
ピーマンや小松菜、ほうれん草など、苦味のある野菜を「苦い」と感じやすいのはそのためです。
※大人がコーヒーやビールを飲めるようになるのと同じで、味覚は成長とともに変わっていきます。
見た目や食感も大切
「緑!葉っぱみたい!」と見ただけで拒否してしまう子どもも多いです。
嫌いだからこそ、クタクタまで煮込む傾向が強い家庭がありますが、逆効果になる場合が多いです。シャキッとした食感が残る方が、噛む練習にもなり食べやすくなります。
過去の記憶や経験が好き嫌いに影響することもある
子どもたちの好き嫌いは見た目や味だけでなく、過去の経験や記憶から影響する場合があります。
楽しい記憶があれば思い出補正がかかりよく食べたり、嫌な経験があると拒否してしまうこともあります。
子どもの野菜嫌いの鬼門は3歳から

子どもの野菜嫌いは1歳を過ぎれば徐々に増えてきますが、一番大変な時期は3歳前後です。
なぜ3歳で野菜嫌いが目立つのか?3歳ごろになると、満腹中枢 が発達し始めます。満腹中枢が発達すると、自分で量を調整できるようになります。
その結果、子どもは
- 「これは食べるけど、こっちは食べない」
- 「ピーマンは嫌いだからいらない」
- 「唐揚げはもっと食べたい!」
と、自分がどの野菜が好きで、どの野菜が嫌いなのか、わかるようになります。
この選択肢が生まれることが、3歳児の野菜嫌いを目立たせる大きな要因です。
3歳児の野菜嫌いを克服!今日からできる5つの方法

①野菜の切り方や形を工夫してみる
同じ野菜でも、切り方や調理法によって食べ具合が大きく変わります。
例えば、にんじんをそのまま煮ると食べない子でも、細かく刻んでハンバーグに混ぜるとペロリと完食することも。
星型やハート型など、見た目がかわいくなるカットにするのも効果的です。
②野菜の調理方法を変えてみる
例えば、小松菜が苦手な子がいるとします。スープに入れても、炒めても食べない。でも天ぷらやポタージュなら食べられる。
いろんな調理方法がありますが、スープに入れた小松菜を食べないのは、ふにゃっとした食感が嫌だったのかもしれません。
でも、天ぷらのように、高温で短時間で仕上げると、シャキッとした食感が残ります。
野菜の好き嫌いは味や見た目以外にも、食感も大事です。野菜嫌いで困ってる時は、食感を変えてみてはどうでしょうか?
③一緒に料理・買い物をして食べる意欲をアップ
子どもはお手伝いが好きです。大人にとっては、「これでいいの?」と思うような小さいお願いも、子どもは達成感を感じとても喜びます。
嫌いな野菜を一緒に買ったり、洗ったりしてもらい、食べる前に「◯◯ちゃんがお手伝いしてくれた野菜だね」
そんな風に言ってあげると、「自分の野菜だから食べる!」と楽しそうに食べてくれますよ。
また、普段はあまり買わないような野菜も、旬の野菜がセットで届くオイシックスなら簡単に手に入ります。普段と違う野菜に触れることで、食育にもつながり、子どもの好奇心や挑戦意欲を引き出せます。
④甘味・塩味・うま味を活かす調理法
味覚には、甘味・塩味・うま味・酸味・苦味の五味があります。
子どもは玉ねぎ、人参、イモ類などの、甘味・塩味・うま味は、本能的に好み、酸味・苦味は、毒や腐敗を察知する味覚のため、慣れるまでは嫌いな子が多いです。
小松菜やピーマンなど、苦味のある野菜は、調理や味付けの工夫がとても大切です。
とはいえ、とはいえ、毎日の食事でこれを続けるのは簡単ではありませんよね。
⑤少しずつ成功体験を積ませる
野菜を完食させるのを目指すのではなく、挑戦したことをほめることが大事です。まずは苦手な野菜はひと口食べればOK、徐々に0から1、1から2と成功体験を重ねることで、自分で挑戦していくことを覚えます。
子どもの野菜嫌いは学習によって決まる
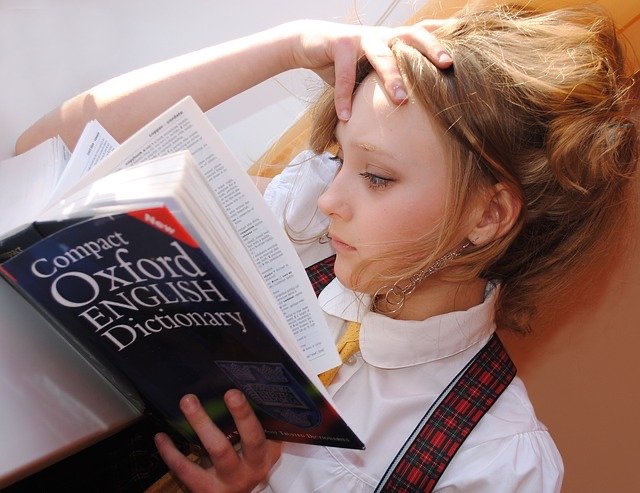
自我が芽生えると、好き嫌いが増えますが、子どもの嫌いは味よりも経験による部分が大きいです。
例えば、
- 食べた後に体調が良くなった・悪くなった
- 食事中に楽しかった、嫌な気持ちになった
こうした記憶が積み重なり、「その食べ物をどう感じるか」が決まっていきます。子どもの食経験は、大きく分けて次の4つの学習によって形づくられます。
安全学習

大人でも、見慣れない食べ物には少し身構えてしまいますよね。それは、子どもも一緒です。
子どもは初めての食べ物が多いので、いろんな食べ物をあげるより、繰り返し食べて、しっかり土台を作ってあげましょう。
「これ食べて美味しい!」そう思えば、次からも安心して食べられるようになります。
嫌悪学習

食べた時に嫌な思い出があると、見た目だけで拒否してしまいます。
無理やり食べさせられた経験や、食べたあとに体調が悪くなった記憶があると、「その野菜=イヤなもの」と結びついてしまうのです。
嗜好学習

嫌悪学習とは反対に、良い経験があると、その食材自体を好きになることもあります。
風邪のとき食べたら、体調が良くなった・治ったなど、良い思い出があるものは、食材の味自体を好きになる事があります。
連想学習

子どもが野菜を嫌がる理由のひとつに、「連想学習」があります。
家族みんなで作って、楽しく食べた。
楽しい食卓のイメージがあると、その時食べた食べ物も好きになりやすいです。
反対に、怒られながら食べた、無理に食べさせられた、という記憶があると、野菜そのものが嫌いになってしまうこともあります。
「野菜=イヤなもの」というイメージがついているときは、無理に食べさせる必要はありません。少しずつ「楽しい」「おいしい」という経験に書き換えていくことが大切です。
子どもの野菜嫌いを助けるおすすめレシピ【ナス・ピーマン・しめじ】

せっかくごはんを作ったのに、食べてくれないと切ない気持ちになりますね。
いったいどんな料理なら食べてくれるのか…
今回は子どもの野菜嫌いランキング上位の【ナス】【ピーマン】【しめじ】の3種類のレシピをご紹介します。
「手作りしたいけど、今日は時間がない…」そんな時は、オイシックスのカット野菜や子ども向け食材セットを使えば、すぐに野菜たっぷりメニューが作れます。
ナスが苦手な子におすすめレシピ
ジューシーな豚ひき肉を使った辛味のない麻婆茄子です。ナスに甘辛い味が染み込み、子どもが好きな味付けに仕上がっています。子どもも喜ぶ ご飯が進む麻婆茄子
いつものカレーにナスを入れてあげると、味や食感の抵抗なくなるので、食べてくれます。ナスと玉ねぎのひき肉カレー
チーズやカレーと言った、子どもが好きな食材や料理と合わすことで、食べるきっかけを作りましょう。
『○○ちゃん、この料理にナスが入ってるんだよ。』
『ナスが入った料理食べれたね!』
その時に、しっかり声をかけることを忘れずに。
声をかける事で、ナスを食べた時の美味しい!という気持ちを覚える事ができ、次から食べるきっかけになります。
ピーマン嫌いを克服する料理の工夫
クタクタになったピーマンより、シャッキ!としたピーマンの方が、食感のアクセントがあって食べやすいです。無限おつまみ ピーマンの塩昆布和え
細かく刻んで味付けごはんに混ぜると、ピーマンの苦味が少なくなるので、食べやすいです。ピーマンとしらすのおにぎり
しめじの風味を活かした食べやすい調理法
しめじは香りが強いため苦手な子も多いですが、醤油やバターと合わせて風味を生かすと食べやすくなります。バター香るにんじんとしめじの簡単炒め
フニャっとした食感が苦手な子も多いので、クリームスープに入れるのもおすすめ。簡単 きのこのクリームスープ
しめじに限らず、キノコ系は主張の強い食材です。調味料をうまく使って、食べやすくしていきましょう。
3歳の子どもが野菜を食べない時のQ&A

Q. どうして緑色の野菜は嫌いなのか?
A. 赤やオレンジなどの暖色系は食欲をそそりますが、緑は草や葉っぱのイメージが強く、味も苦みのあるものが多いです。また見た目が似てる野菜が多く、何の野菜なのかわからずに食べている可能性が高いです。
野菜の名前を教えながら食べて、緑の野菜と一括りにならないようにするのがおすすめ。
Q. 子どもの野菜嫌いに果物で代用はできる?
A. 基本的にはおすすめできません。
野菜と果物は栄養価を見ると、共にビタミンやミネラルが豊富ですが、果物は糖度が高いため、食べ過ぎは肥満につながる恐れがあります。
サラダにフルーツを混ぜるなど、料理の一部として使ってもいいですが、フルーツがメインになってしまうと、ますます野菜を食べなくなります。
Q. 苦手な野菜は克服した方がいいのか?
A. 苦手な野菜があっても、ほかの野菜で栄養価が補えていれば無理に克服させる必要はありません。
無理強いするとますます食べなくなるので、食べるきっかけがあれば少しずつ挑戦してみましょう。
まとめ

3歳の子どもの野菜嫌いは、決して珍しいことではありません。
大切なのは、
無理に食べさせようとしないこと、小さな「食べられた」を積み重ねること、そして、楽しい食卓の雰囲気をつくること。
ちょっとした工夫で、子どもが野菜を食べやすくなることも多いです。
今日からできる工夫を試して、毎日のごはん時間をもっと楽しくしましょう。
今回もご閲覧ありがとうございます。
よしみけ٩(ˊᗜˋ*)و




コメント